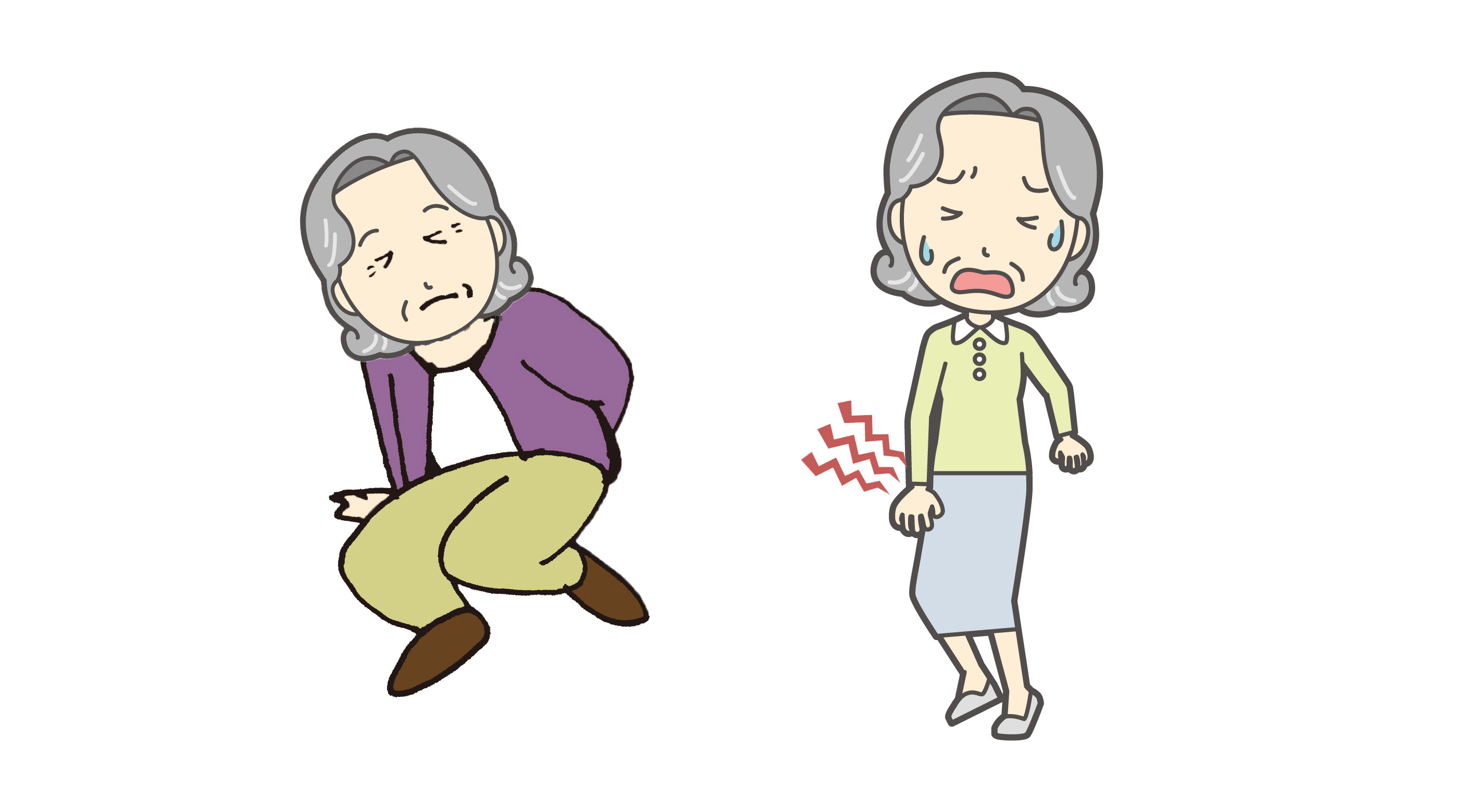71才の女性、自営業の方です。平成29年12月25日に自宅廊下で右側に転倒しました。しかし、翌日までは普通に歩けていたとのこと。27日からは台所仕事は椅子に座ってするようにしたそうです。1月5日に両側大腿部内側痛が悪化して自宅内も歩行困難になり、当院を受診されました。
赤丸領域に痛みを訴えられていましたが、レントゲン像は異常を認めません。右恥骨部に圧痛を認めました。
1月8日(初診3日後)にMRI検査を施行しました。STIRという条件で、骨盤の冠状断(前後からみた像)です。
同じくSTIR条件で水平方向に切った画像です。
STIRという条件での画像ですが、本来骨は黒く描出されますが、赤丸領域は骨が白くなっています。これは骨が損傷しており、骨内に出血している状態となります。青丸領域は正常例の比較の領域となります。冠状断で骨の周辺も白いのは(オレンジ矢印)筋層内への出血です。右恥骨と両側の股関節部の骨折です。このような状態では骨折であることを理解して生活することが重要です。できる限りの安静をとっていればどうにか伝い歩きは可能であることが多く、1か月程度で自宅での生活には支障がなくなりますが、骨折と診断されずにシップを貼るだけで普通の生活を続けようとするといつまでも痛みが軽減しないことになります。この患者さんも初診から1か月の2月8日には杖歩行が可能となり、2か月後の3月3日に日常生活での支障がなくなったと報告を受けています。
次は91才の女性で同様の骨盤骨折の方ですが、歩行困難の状態の中でかかりつけの総合病院の整形外科医に心ない言葉を浴びせられることになりました。
令和5年12月に転倒し右大腿骨頚部の骨折を受傷されました。大腿骨頚部骨折とは高齢者が転倒して受傷しやすい骨折で、手術をしないと歩行可能とならない重症の外傷です。総合病院で手術を受けられ、退院後も定期的に術後の診察を受けていました。右大腿骨頚部骨折の手術後、1年2か月後の7年2月2日に自宅玄関で転倒し、翌日同病院を受診されました。レントゲン撮影を受けて「異常はない、心配いらない」と診断されました。
レントゲンは当院での初診時のものです。5日経過した2月7日に痛みは増悪し、歩行困難となりました。この経過は前記の71才の自営業の方と同じです。患者さんにとっては1年2か月前の右大腿骨頚部骨折と同じような痛みで、また手術が必要になるんじゃないかと心配せずにはいられない状況であったのではないかと推察します。5日前に診察を受けたばかりの患者さんは担当医に電話で相談したところ、「心配ないと伝えたはずだ、もう連絡してくるな。」と言われてしまったそうです。「どうしたら良いですか。」と尋ねたそうですが、「自分で診察してくれる医院を探せばいい。」とも言われてしまったそうです。何とも悲しく切ない話です。知人に相談したところ当院を紹介され、2月7日に受診されましたが車椅子での受診でした。
MRI検査を行うと、STIRの条件で右股関節部が白くなっており(赤丸領域/青丸は健側の同じ領域)、骨折と診断されました。71才自営業の女性と同じ骨折です。水平に切った画像でも健側の青丸領域に比較して赤丸領域が白くなっています。4週後の3月7日に屋内歩行が可能となりました。6週後の3月21日には寒いと痛むが、日常生活には支障はなくなったとのことでした。71才の自営業の方に比較すると回復は早いのですが、71才の女性の骨折は両側性であり、この方は右側のみの骨盤骨折であることによるのではないかと推察します。私はこのようなレントゲン像では診断できないけれど、歩行困難となる骨盤骨折を20例近く診てきていますが、レントゲンだけで診療している医師は、総合病院の整形外科医も含めこのような骨折を認識しておらず、患者さんの不安を無視し「打撲だ、心配ない」と診断してしまうのです。
6週後のレントゲン像では(下拡大図・赤矢印で)右恥骨骨折が明瞭となっており、仮骨形成も確認されます。上拡大図では右股関節部の骨内も白くなっており骨内の仮骨が形成されたことが把握できます。
総合病院の整形外科医がこの患者さんを術後1年経過しても定期的診察を行っていたのは何のためだったのかと思いました。患者さんに寄り添うためではなく、自己満足のために患者さんとその家族に受診という手間と費用をかけさせているだけとしか理解できません。レントゲンのみで骨折が診断できると考える医師が”自分の技量は絶対であり、訳のわからない訴えをする患者はおかしな患者も多い”と思っている整形外科医師は、この患者さんに投げつけたような言葉を平気で言ってしまうのだと推察します。私自身も病院勤務医時代はそのようであったかもしれません。忙しい業務の中で勤務医は効率的な業務対応を求められているからです。
しかし開業医となり、患者さんの言っている病状は真実であり、自分がそれを認識できる知識と経験がない可能性を前提に診療しているいう姿勢で患者さんに向き合うと、このようなレントゲンでは診断できない患者さんが極めて多くいることを知ることになりました。どんな時も医師は謙虚な姿勢で患者さんに向きあわなければいけないと反省させられる事例です。